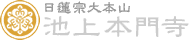池上本門寺を味わう
その他
池上本門寺周辺にある見所をご紹介します



池上本門寺の西方に位置し、丘陵の高低差を利用した大田区立公園。園内には350本を越す梅が植えられ、例年1月~3月頃、大田区の花「梅」が春の訪れを知らせ、多くの人に親しまれている。また、園内にはツツジ約800株をはじめとする樹木や、茶室、和室の施設、水琴窟もある。
池上梅園は、大田区の施設であり、池上本門寺の付帯施設ではありません。お問い合わせは、下記、池上梅園事務所までお願い致します。
- 開園時間:9:00~16:30
- 休園日:2月・3月を除く月曜、年末年始(月曜日が休日の場合は次の平日)
- 入園料:大人(16歳以上65歳未満)100円 小人(6歳以上16歳未満)20円
- 駐車場:公園前にコインパーキング有り
〈関連サイト〉



池上本門寺の東方に隣接する、大田区立公園。池上本門寺の寺領を1938年に東京市(当時)に移管し、現在に至る。園内には弁天池やデイキャンプが出来る施設など、池上本門寺の緑と共に大田区民にとって貴重な憩いの場となっている。
〈関連サイト〉


小麦粉を発酵し熟成させて出来上がるくず餅は、ぷるんとした食感が堪らない和菓子です。特に江戸時代から続く「くず餅屋御三家」が有名です。池上本門寺参詣の帰りに、江戸の昔に思いをはせながらちょっと一服したり、味較べなどするのは如何でしょうか?
- 浅野屋本舗:東京都大田区池上6-2-15
- 藤乃屋:東京都大田区池上4-25-7
- 池上池田屋:東京都大田区池上4-24-1


ホンモンジゴケとは、1910年(明治43年)共立薬科大学・桜井久一博士が池上本門寺の五重塔周辺で発見した新種の藻類で、発見された場所にちなみ和名を「ホンモンジゴケ」と命名されました。この苔は、五重塔の屋根から流れる緑青部分に生息し、現在でも大切にされています。
〈関連サイト〉