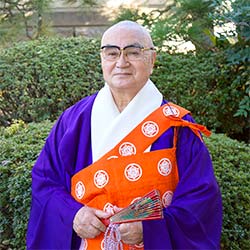
一向に南無妙法蓮華経と称えせしむべし(四信五品抄)
先月号に続いて富木常忍氏へのお手紙で示されたご教示をご紹介いたします。建治三年(1277)4月1日、身延の地からのご返信が今月ご紹介の聖語であります。
富木氏が法華経、日蓮聖人の大信者であります事は毎々申し上げておりますが、その富木氏から大聖人への質問状が届きます。それは、
?佛道の安心を得るためには日常でどのように修行すればよいか。
?肉食のあとの読経してよいか。
?肉食し一宿のあとの読経は。
?五辛(ごしん)(五葷(ごくん)とも。にんにく・らっきょう・ねぎ・ひる・にら)を食して、行水せずに読経はどうか。
?不浄(清らかでない)の時、堂内に入り読経。
?不浄の身でも毎日読経してよいか。
?月一度でも精進清浄にして読経すべきか。
?不浄の身に袈裟をつけることはどうか。
?不浄(不幸)の時の自分の思いをどのようにすればよいか。
というものでありました。何と清らかな、何と深い信仰心でありましょう。そして、その一つ一つが七百年後の今日の私達佛道修行する者にとっても相通づる、いや反省を促しているご教示と拝します。と申しますのも、質問の九カ条の全てが今日の私達に当てはまるからであります。僧侶である私にとりましても耳の痛い、反省の九カ条であります。
この質問に対し、日蓮聖人は一々の御返事ではなく、仏道修行の根幹についてお述べになられたのが四信五品抄であります。その概略をご紹介しますと、
?末法の時代における法華経修行者の安心の世界。
?末法の時代における法華経修行者の心得。
?仏教と国家の興亡について
お述べになられます。
その中でお釈迦様ご在世の時に説かれたお経文を四つの領解にわけて説明なさったのが「四信」。「五品」とは仏様ご入滅後に残された経典を通じてその内容を自らの修行をどのようにしていくか五つの教説のこと。その上で法華経・お題目こそが唯一の道とお説きになられ、そして四信・五品に区別はない。一念(いちねん)信解(しんげ)(ひたすら信じ唱える)以信代慧(いしんだいえ)(信じる力が智慧に勝る)だからあれこれ考えずひたすらお題目修行に励みなさいとお説きになられるのであります。
そして今月ご紹介の聖語
「私たち修行者は常にこれで良いのかの疑問を持ち続けている。そのことは仏道修行者として当然の事である。その上に立って、ひたすら法華経を信じお題目をお唱えする事、この事こそが末法の時代に生きる仏道修行の基本なのである。」
「法華経・お題目のお力を信じ切り、任せきってひたすらお題目をお唱えなさい」
今月の聖語は私たちが真面目に取り組めば取り組むほど湧いてくる疑いに対する大聖人からの「呼びかけ」であります。